被相続人は「遺言書」を作成することで、相続の内容について希望通りに決めることができます。具体的には、相続分・遺産分割禁止の指定、財産の遺贈、相続人の廃除、子の認知、遺言執行者・後見人の指定などを、遺言書に記載することで行うことができます。遺言書は、法律上の要件を満たせば有効となるため、法定相続人以外の特定の者に全ての遺産を相続させる、という内容の遺言書であっても有効となります。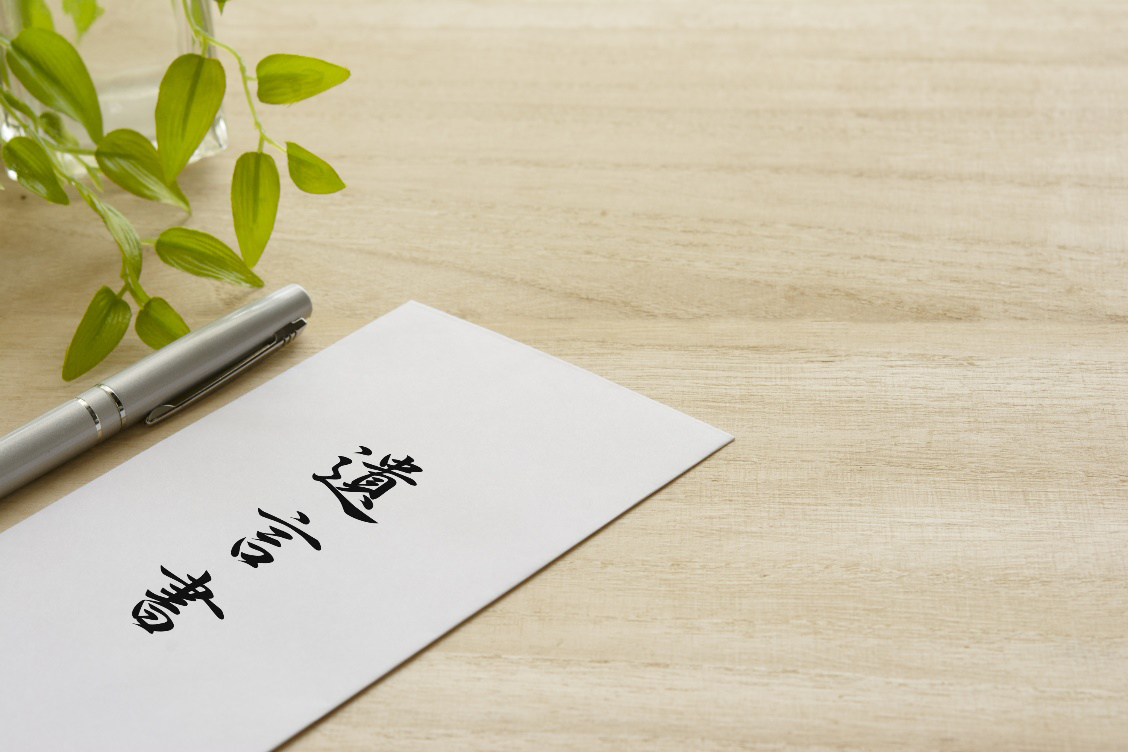
もっとも、一定の法定相続人(被相続人の配偶者、子(及びその代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等))、すなわち遺留分権利者には、遺留分侵害額請求が認められています。「遺留分」とは、遺留分権利者について、法律上得ることを保障されている最低限の遺産の取り分をいい、遺留分侵害額請求とは、遺留分よりも相続する遺産の割合が少ない場合に、その不足分を請求することをいいます。
この制度の趣旨は、本来相続をするはずの相続人が最低限の遺産を取得できないという事態を回避し、残された家族を保護する点にあります。したがって、遺言書であっても、遺留分権利者の遺留分を侵害することはできません。
遺言書に、遺留分権利者の遺留分を侵害するような相続の記載があったとしても、その遺言書は有効です。しかし、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすれば、その遺産の受取人から不足分を取り戻すことができます。例えば、被相続人が遺言書において、「全ての財産を愛人に相続させる」と書いていたとしても、被相続人の配偶者や子は、それぞれの遺留分に応じて、愛人に対し不足分相当額を請求できることとなります。
このように、基本は遺言書の通りに遺産分割や相続手続きを行うことになりますが、遺言書というのは、あくまで財産や相続につき被相続人の意思を尊重するためのものであるため、その内容に納得がいかない場合には、遺言書に従わないこともできます。具体的には、相続人全員が同意すれば、その遺言は効力を失います。また、遺言で、相続人以外の者に財産が残されている場合には、その相続人以外の者の同意があれば、遺言に従わずに遺産分割することができます。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続問題に関する相談を承っております。「限定承認と相続放棄のどちらを選べばいいかわからない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
遺言書にはどれくらいの効力があるか
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
-

会社廃業・...
会社廃業・休業・倒産は、それぞれ違います。 ■会社の廃業とは 会...
-

時効取得等...
所有権や不動産賃借権は時効によって取得することが出来ます。 時効に...
-

成年後見制...
■成年後見制度とは 成年後見制度とは、認知症や知的障害などによ...
-

相続登記の...
ニュースなどで相続登記が義務化されると聞いたことはあるでしょうか...
-

土地や空き...
▼ 相続放棄とは 「相続放棄」とは、亡くなった故人の遺した財産を法...
-

認知症の相...
相続手続きの中には、相続人全員の関与が必要な手続きが存在します。...
-

不動産の共...
相続登記は不動産を相続する際に大変重要となる手続きであり、202...
-

相続放棄の...
相続放棄をしたい場合は、少なくとも以下の必要書類を被相続人の住所地...
-

相続を司法...
遺言の作成や相続税の申告も、間違いなく進めるのはなかなか大変なこと...
八木貴弘司法書士事務所の主な対応地域
東京都全域の市区町村(23区含む)、その他地域も御相談の上対応可能です

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|遺言書にはどれくらいの効力があるか